工作
絵画や設計図のように2次元の情報が重要視されてきたのは解る人に解ればよいという考えがあったからです
田舎道の絵を見ただけで、わかる人にはその道の下の地質が調査報告書を読むように類推できます
原子爆弾はE=mC^2というわずか6文字からつくられたと書かれています
数学になると解けるか解けないか、YesかNoかさえ証明できれば、あとの膨大な解法は解ったも同じといいます
遺伝子工学も1ページ程度の論文で全てが始まったのです
解る人には、2次元の絵や設計図ですらなく、ほんの数行の文字で全てがわかるのです
わかる人同士の合い言葉、それが業界用語だったり腹芸だったりするのでしょう
問題はそれではわからない多くの人のことです土木構造物はその大きさから、いったいどれくらい丈夫なのか、それとも脆いのか、一般にはわかりづらいものになっています
構造計算書をいくら読んでもいっこうに体で理解できない人は自分だけではないとおもいます
許容応力度やたわみ量や共振振動数などの数字だけで強度特性に自信がもてる人は、絵を見ただけで地下のことが類推できる専門的な才能を持った人だとおもいます
そういう人は少数です
多くの人は釣り竿やゴルフクラブを選ぶときのように、振り回したり撓らせたりして強度特性を身体で感じることでモノの構造を把握しているのではないでしょうか
理解できないモノにまわりを取り囲まれるという状況は、あまり心地の良いものではないでしょう
大きな構造物でも縮小すれば多くの人に土木構造物が理解してもらえるとおもいます
公共事業とはまず理解すること
だいぶまえおきが長くなりましたが、ここに試作模型の意味が出てくると思います
大きな構造物でも縮小すればその強度特性などが計算値でなく実感として把握できます
また、ここで紹介するように土木構造をまねた画板だとか机だとかが工作できるようになるとおもいます

アーチ橋の橋桁
(横桁、縦桁、横構)
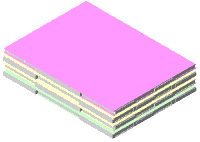
カメ板の3D図

折り畳みパソコン机